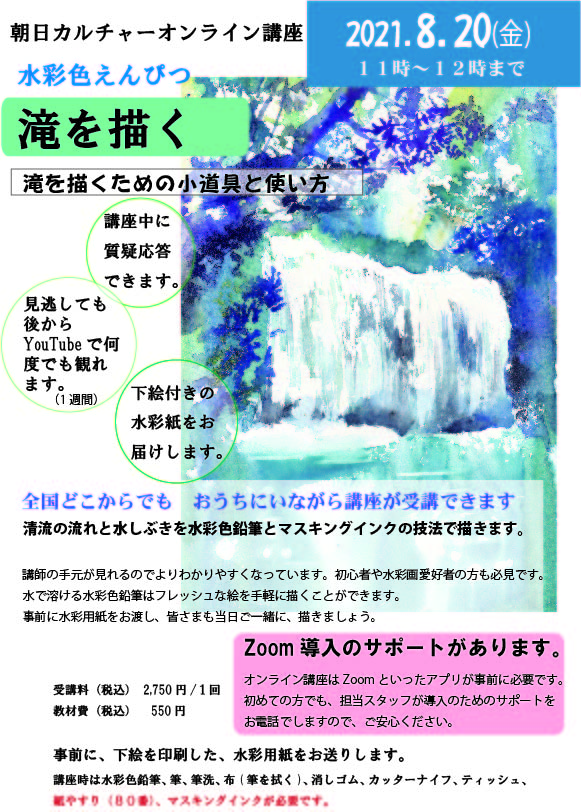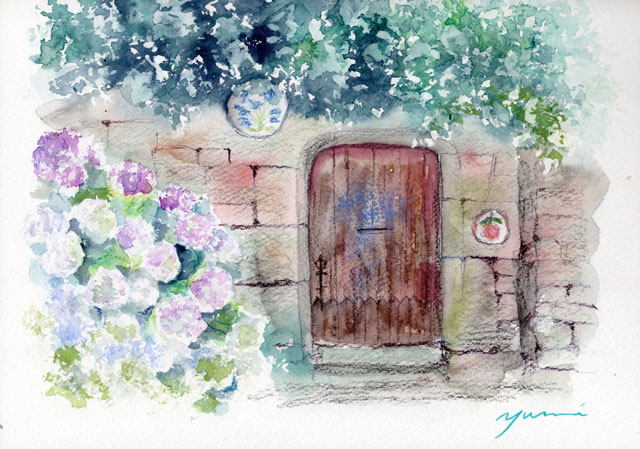流れる雲を描く

雲が流れる空を描きます。
その下は、薄(すすき)が続いています。
point
空のグラデーションをします。
グラデーションの後はすぐに、雲を描きます。
雲の中にも影を入れていきます。
その際に、綿棒がベストです。
細かく、しっかりと影が入ります。
また、薄は細く長くマスキングで描きます。
竹ペンをおすすめします。
細く、長く描くにはちょっとしたコツが必要です。
マスキングの使い方と竹ペンの使い方をお伝えします。
(使用した色)
110.120.157.247.151.180.187.168,184,177,137(249),168,274,275,177
綿棒お持ちください。
ファーバーカステル アルブレヒトデューラー水彩色鉛筆 色番号表記